第7章 未来へ向けて
2010年~2023年

1.リーマン・ショックを乗り越えて
リーマン・ショックを乗り越えた日新工業株式会社は、新たな事業として2010年(平成22年)、山形工場において特殊硬質アスファルトの製造を開始した。これは山形工場の遊休地を使用した防水以外の事業であり、それは山形工場の強い意欲と知恵により、自分たちで新たな設備を考案し、自社で作り上げたものであった。技術部で配合が検討され、工場での試作には、当時の山形工場工場長であった江口俊明(のちに取締役生産部長を務めた)を中心に、営業統括部長の菅野司(のちに専務取締役を務めた)、技術部長の関原克章、生産部長の相臺志浩(現在の社長)が立ち会い、一緒になって試作品を作り上げていく中で、本社と工場との間に一体感が生まれた。この事業によって、前年に退職を余儀なくされた山形工場で働いていた元社員の一部を呼び戻すことができたことは、私たちにとって非常に喜ばしいことであった。
同年、日本アスファルト防水工業協同組合の仕様として、改質アスファルトトーチ工法「ベストーチ工法」を発売した。この工法は従来の「メルタン21工法」よりも、裏面のフィルムを融けやすくした製品であり、当初は1㎜程度の穴を開けたフィルムを採用していたが、のちに特殊なフィルムに変更している。
そのような中、翌2011年(平成23年)3月11日、東日本大震災が発生する。
幸いなことに埼玉工場、山形工場ともに大きな被害は受けなかったが、燃料の調達に苦労することになった。この時、大阪市や名古屋市で日新工業の製品を輸送する運送会社や、多くのサプライヤーの尽力を得て、燃料に使用する重油を確保することができた。このことは、損得を超えたサプライヤーとの共助を忘れてならないと、改めて感じた出来事であった。
またこの頃、日新工業は組織改革に乗り出した。
まず、2011年(平成23年)には執行役員制度を導入し、翌2012年(平成24年)には人材育成への取り組みとして階層別教育制度を開始した。これは「企業が成長するためには社員一人ひとりの成長が大切であり、その個人や役割に合った教育が必要である」という理念からきたもので、この後、さまざまな研修制度を積極的に取り入れていった。
2.中期経営計画2013、2018の策定
2012年(平成24年)には外部の経営コンサルタントからアドバイスを受け、各部署で経営戦略について議論、検討を重ねた。そして、翌2013年(平成25年)同年1月から5ヵ年の経営計画である「中期経営計画2013〜21世紀の防水トップメーカーを目指して〜」をスタートさせた。この計画では「魅力ある良質な製品の供給と活力ある組織の構築を図りながら、収益の改善を目指した」というものであった。
二度にわたる事業再構築で低迷していた研究開発部門は、この頃から毎年人員を増強するとともに、大手化学メーカーに長年勤務した技術者たちを招き、指導を仰いだ。このことが功を奏し、現在も若手社員の活躍によって部内が非常に活気づき、新製品・新工法の開発と既存製品の改善を意欲的に進めている。
その成果の一つとして、防水材料メーカー単独として初めて、日本工業規格(現在の日本産業規格)JIS K 2207「石油アスファルト」防水工事用アスファルトを取得した低臭低煙の「シグマートEL」を2014年(平成26年)に、屋内防水向けに開発した湿気硬化型アスファルト防水「クリンアスNEO」を2017年(平成29年)に発売している(第6節参照)。さらに同年には、火を使うことなく現場で溶融可能なアスファルト電気溶融機「エコドリッパー」を上市した。また、セラミック製の保水パネル「カナートグリーンビズ」と「セダム緑化」を一体化した、緑化パネル省管理型屋上緑化システム「カナートグリーンビズG」も2012年(平成24年)に発売した。
屋根下葺材では2014年(平成26年)に、1.0㎜厚の片面粘着層付ルーフィング「カスタムライト」を発売した。この製品は16㎏と軽量で釘穴シーリング性が高く、大型施設の屋根下葺材として普及していくことになる。
2016年(平成28年)には、全国防水リフレッシュ連合会から「アスファルト環境対応型防水改修工法」がスタートし、湿気硬化型アスファルト「アスコート」を用いた「立上り非撤去工法」を上市した。
翌2017年(平成29年)には、中堅若手の意見を取り入れるプロジェクトチームを立ち上げ、日新工業の強みと弱みを分析しながら経営戦略を練り上げた。これを受けて、翌2018年(平成30年)1月から3ヵ年の経営計画である「中期経営計画2018〜一致団結 100年企業の創造と挑戦」をスタートさせた。本業である防水事業に経営資源を集中しつつ、新たな経営の柱を創造することで、着実な業績改善を目指した。
また、新たな試みとしては、近年の人手不足を補うため、2018年(平成30年)から大学を卒業したばかりのベトナム人を正社員として埼玉工場で登用した。
この頃の外国人の雇用は最長3年から5年で帰国しなければならない「技能実習生制度」が一般的だった。短期間しか滞在できないため、技能の蓄積がなされないことと、何より低賃金で劣悪な雇用環境の中で働くということが問題視されていた。日新工業はこの技能実習生制度ではなく、長い期間にわたって働くことができ、日本人の大卒社員並みの賃金を支払う「高度人材制度」を活用することにした。これにより、工場の技術力の向上はもちろんのこと、ベトナム人が安定した収入源を得られるように配慮した。この働き甲斐を重視した雇用により、彼らはやる気を発揮し、数年で日新工業にとって大事な戦力へと成長した。
かつて相臺宗次郎が掲げた「人間を分けへだてしない」という精神は、現在でも深く息づいているのである。
さらに同年には、埼玉工場が環境マネジメントシステム国際規格「ISO14001」認証を取得した。
3.第6代社長・相臺志浩の就任と改善活動
2019年(平成31年・令和元年)は、日本の皇室が代替わりするなど、世間でも世代交代の機運が醸成され始めてきた。日新工業においても社長の相臺公豊が会長に就任し、第6代社長に45歳の相臺志浩が就任した。防水工法の多様化、施工者の人手不足、収益性の改善、改修工事の台頭、そして環境対策など、さまざまな課題に取り組んでいくこととなった。
 | ||||
| 1973年 | 千葉に生まれる | |||
| 1997年 | 明治大学経営学部経営学科卒業 日新工業入社 埼玉工場製造Ⅰ課勤務 8月に山形工場へ転勤 | |||
| 2001年 | 営業統括部営業企画課 | |||
| 2005年 | 生産部部長就任 | |||
| 2011年 | 常務取締役、経営戦略部部長就任 | |||
| 2013年 | 専務取締役就任 | |||
| 2019年 | 代表取締役社長就任 | |||
この年、埼玉工場の改質アスファルトルーフィング製造8号機の改造を行った。1988年(昭和63年)に導入したこの8号機の欠点を直すため、アメリカから再び最新鋭の設備を導入し、生産性向上と製品品質向上を図ることとなった。だが、この新しい設備の稼働は当初は困難を極めたが、当時の埼玉工場の工場長であった鈴木量(のちの生産部長)をはじめ、工務課長の伊藤友康、そして8号機の第一線で働く社員たちの尽力によって見事稼働に至った。その中には、試験製造中に顔に大やけどを負いつつも、病院から戻ってなおも稼働にこぎつけようと必死に努力した班長の姿もあった。


同年には、この8号機から日本アスファルト防水工業協同組合の専用品である環境配慮型改質アスファルト防水「アスオーブ工法」(無釜タイプ)の製造が開始された。
このアスオーブ工法は、アスファルト防水熱工法と改質アスファルト防水粘着工法を組み合わせた複合工法であるが、このフィルムの選定には技術部と生産部が何度も検討と試作を繰り返し、ようやく発売にこぎつけている。結果として、建設会社からの評価も高く、着実に施工実績を伸ばしている。

また、環境省が推進する省エネ住宅の普及により、高断熱が要求される中、硬質ウレタンフォーム断熱材である「シェーンボード」が、前年からの準備を経て、建築用断熱材の日本工業規格(現在の日本産業規格)であるJIS A 9521「建築用断熱材」の認証を取得したのも、アスオーブ工法を発売した同じ年の出来事である。これより少し前の2017年(平成29年)には、山形工場工場長の田中英夫を中心として、技術部やサプライヤーとの共同開発により、断熱性能の高い次世代発泡ガスを用いた新しい「シェーンボード」の開発に成功し、製造を開始している。
近年の地球温暖化による露出防水へのさらなる熱負荷を軽減するため、防水層の表面に塗布するトップコートを遮熱塗料「プレノカラー遮熱」へ全面的に切り替えたのも同じ年であった。さらに、フリーアクセスフロアシステム「PFシステム」が2018年度のグッドデザイン賞を受賞したことも、この年の大きなニュースであろう。
すでに数多くの建築物でPFシステムは使用されていたが、グッドデザイン賞の受賞は、その高い機能性とデザインが内外に認められたことを意味し、ベルギーのブゾン社とともに喜びを分かち合った。
そして、2020年(令和2年)に開催が予定されていた(翌2021年に開催)東京オリンピック・パラリンピックの競技施設の一つである(新)国立競技場、加えて選手村の宿泊施設にも、日新工業の製品が採用された。


4.新型コロナウイルス感染拡大と中期経営計画2021の策定
新しい社長が誕生し、順風満帆な船出に見えたが、2020年(令和2年)の新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大によって事態は大きく急変した。この年の3月以降、営業・管理部門は在宅勤務を強いられ、埼玉工場、山形工場ともに一時帰休を余儀なくされた。さらに、原油価格高騰による原材料価格の上昇で、厳しい事業環境に直面することになった。
そのような中、日新工業は2021年(令和3年)に3ヵ年計画「中期経営計画2021〜21世紀の防水トップメーカーを目指して〜」をスタートさせた。この計画では、「情熱」を持って他社に負けない、社会的に価値のある製品やサービスをお客様に提供することを目標とした。そして、「時代の流れに乗る=「波乗り戦略」」「新しい市場を作る=「フロンティア創造」」「既存製品を完璧にする=「あきらめない価値創造」」「経営の柱をたくさん作る=「多柱経営」」の四つを経営計画の柱として掲げた。
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、テレビ会議やテレワーク、情報共有システムの導入など、日新工業にデジタルトランスフォーメンション(DX) 化の端緒をもたらした。社内のDX化は始まったばかりであるが、デジタル技術を有効活用して効率化を図ろうとしている。
デジタル戦略の一環として、まず同年に、日新工業のホームページを大幅にリニューアルした。新たな「人の暮らしを守る、総合防水メーカー日新工業」というキャッチフレーズを掲げ、動画を用いて「ものづくり企業」であることを前面に押し出した。
また同じ年、日新工業として初めてのオンラインセミナーを開催した。第1部として妹島和世氏、内藤廣氏、青木淳氏など、日本のみならず世界で活躍する著名な建築家を講師に招き、オンラインで講演会を実施した。続く第2部では日新工業からアスファルト防水の基礎知識を解説する講演を行ったところ、大変多くの方にご視聴いただいた。

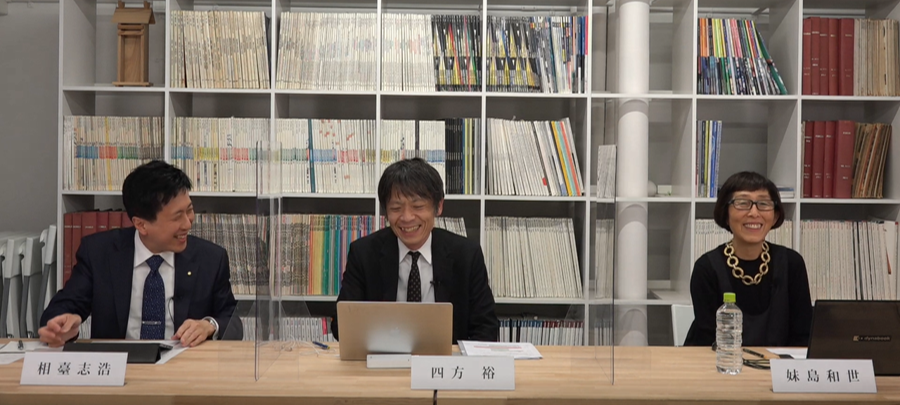
さらに製造設備の改善にも取組み、大手製紙会社OBや大手繊維会社OBのご助言を得ながら、品質向上と採算性向上を目指して山形工場抄紙1号機を約20年ぶりに改造し、破布の離解設備も見直した。また埼玉工場2号機、6号機の改造も進めた。


5.「技術の日新」復活に向けて
このような環境下で長年開発してきた製品が、ようやく日の目を見ることになった。
防水工事分野では、同2021年(令和3年)に日本アスファルト防水工業協同組合の仕様書「アスファルト防水の仕様」が改定され、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)を意識した新しい製品・仕様がラインナップされたので、いくつか紹介しよう。
まず従来の砂付ルーフィングに代わる新しいルーフィングとして、染色メーカーの小松マテーレ株式会社と日新工業の技術陣が数年にわたって共同開発を進めてきた、長寿命ハイブリッド型アスファルト防水システム「アスファインシリーズ」が登場した。これはアスファルトルーフィングの表層に特殊加工したフィルムを貼り付けた製品で、意匠性が大幅に向上した仕上げだけでなく、元来長寿命であったアスファルト防水の耐久性、耐候性はさらに高まった。その第1弾として、新築・改修を問わず粘着層で張付ける「アスファインルーフN」を発売、第2弾として新築工事向けに溶融アスファルトで施工するタイプが発売され、建築物の長寿命化を図るための新時代の露出改質アスファルトルーフィングとして大いに期待されている。改質アスファルト防水の露出工法では高耐用仕様を加えている。この仕様は高い強度と伸びのある加熱溶融型高耐久アスファルト塗膜防水材「アスリードコート」を用いることで、露出防水の想定耐用年数を伸ばすことができた。

また、技術部が何度も配合を検討して湿気硬化ゴムアスファルト防水「クリンアスNEO工法」の大幅な見直しも行われた。ルーフィングを従来品よりも柔らかくし、下地に馴染みやすくしたことが大きな特徴であろう。接着剤兼防水材の役割を果たす「クリンアスNEO」も従来品より大きく改善し、施工者の使い勝手を考慮した設計になっている。
これらの製品や仕様は、建築物の防水材における「カーボンニュートラル」の実現への第一歩といえるかもしれない。
一方、住宅の屋根下葺材分野では、表面がべたつかない改質アスファルトルーフィング「アルバシリーズ」の第1弾として「アルバクリア」が発売されたのも同年である。カラールーフィングを発売してから30年以上が経過していたが、アスファルトの特性上、夏場はどうしても表面が若干べたついてしまい、屋根工事業者の靴の裏に付着してしまうという課題が残っていた。アスファルトの改良によってべたつきはかなり抑えられていたが、地球温暖化により夏場の気温上昇の影響がみられた。だが、このアルバクリアは、表面に特殊な基布を張り付けることで、べたつきをなくし、施工者の作業性向上に寄与している。また特殊な塗料を用いたことによって、他社を凌駕する防滑性・耐べたつき性を有し、多くの方からご好評をいただき、現在急速に販売数を伸ばしつつある。第2弾としてカッパルーフ2号の改良版である「アルバフェイス」も同時に発売した。
同じ屋根下葺材では、片面粘着層付ルーフィング「カスタムライト」において、裏面を剥離紙から剥離フィルムに変更している。万が一、カスタムライトが屋根から滑り落ちて事故を発生させることがないように、この剥離フィルムの検討に数年を要したが、根気強くサプライヤーと交渉して実現させた。これにより、現場でのごみの減量化が図れるだけでなく、粘着性能が低下しにくいという利点も生まれた。また、高耐候アスファルトシングル材(屋根材)「マルエスシングル・エクシード」を発売したのも同年であり、2021年(令和3年)は新製品を矢継ぎ早に発売した年となった。
これら新製品の発売や既存製品の改善は、この10年をかけて育ててきた技術部の社員と、営業、生産を担当する社員たちが意見を出し合い、全社一丸となって成し遂げてきたものである。「技術の日新」復活に向けた取り組みとしてはまだ道半ばであるが、少なくとも「人財」という大きな財産を日新工業は手にしている。
6.未来への飛躍を目指して「Reborn Nisshin」
2020年(令和2年)、新型コロナウイルスの感染拡大は、多くの変異株を生み出しながら長期化した。また、世界各国が相次いで公的資金を投入したため急激な景気回復を招き、投機的資金が市場へ過剰に流れて原油価格が高騰した。さらに2022年(令和4年)には、ロシアによるウクライナ軍事侵攻により価格高騰に拍車がかかった。世界に大きな変化が起こる中で、日新工業もそれに迅速な対応が求められた。このため「中期経営計画2021」から2年、より具体策を盛り込み、抜本的な組織改革を行う3ヵ年計画「中期経営計画2023」をスタートさせ、「Reborn Nisshin」をスローガンに「収益性改善」「マネジメントシステムの構築」「新製品の開発」の三つを経営計画の柱として掲げた。
日新工業は創業から100年の間、いくつもの困難に見舞われてきたが、そのたびに、歴代の社長たちの熱い信念と、それを支えてきた多くの社員たちによる涙ぐましいまでの努力の結集があったからこそ、ここまで乗り越えられてきたと断言できる。そして日新工業を支えてくださるお客様、サプライヤーの皆様にも、この場をお借りして心から感謝を申し上げたい。
日新工業の社名の由来の一つに、中国の古典である四書の一つ「大学」の1節、「苟日新、日日新、又日新(苟に日 に新にせば、日日に新に、又日に新なり)」の銘文がある。
常に新しいことにチャレンジしていくという、日新工業の精神をこれからも持ち続けていきたい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
- 日新工業株式会社編著「アスファルトルーフィングのルーツを探ねて」1984年
- 日新工業株式会社編著 70周年記念誌「NISSHIN the 70th Anniversary」1992年
- 日本アスファルト防水工業協同組合編著「日本アスの40年〜防水の技と熱き思い〜」2004年
- 日本アスファルト防水工業協同組合発行「日本アスだより」
- 社団法人全国防水工事業協会 防水100年史編纂委員会編著「日本の防水 〜 防水工事100年のあゆみ」2005年
- 特許庁監修 発明図書刊行会編「日本発明家五十傑選」1952年
- 相臺宗次郎著「あなたは会社の代表です」1959年
- 日新工業株式会社山形工場有志会「風雪に耐えて 相臺宗次郎翁の歩み」1968年
- 岡崎善吉著「わが生涯の記その2 縁生の人々」1977年
- 比毛関著「旅路」1975年
- 日本石油株式会社・日本石油精製株式会社社史編さん室編「日本石油百年史」1988年
- 経済産業省資源エネルギー庁編「日本のエネルギー150年の歴史」2018年
- 福島県教育委員会ホームページ「うつくしま電子事典」2021年閲覧
- 全国段ボール工業組合連合会ホームページ「段ボール産業の歩み」より2021年閲覧
- 工文社「月刊PROOF 2005年9月号」「防水百年を築いた挑戦者たち“わが社のプロジェクトX”」より2005年
- あさひ銀総合研究所編「ユニーク企業の経営哲学」(第1章)1993年
- 社団法人日本アスファルト協会発行「アスファルト」第40巻第194号 1998年
- 関義城著「江戸東京紙漉史考」1943年
- 満洲日日新聞社 大連日日新聞社発行「満洲職員録」1941年版
- NTTグループ「NTTグループの歩み」2022年閲覧
- 新樹社「防水ジャーナル1992年4月号 最近の勾配屋根と雨仕舞 ALC局舎屋根防水改修工法」1992年
- 総務省統計局 消費者物価指数 2021年年報
- 合資会社鈴鹿商店「昭和十一年度 買原簿」1936年
- 建築資料研究会編「第1回土木建築資料総覧」1926年
- 建築資料研究会編「第2回土木建築資料総覧」1927年
